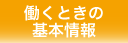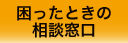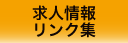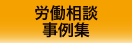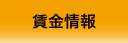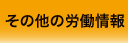7 職場環境
過重労働による健康障害の防止対策
長時間にわたる過重な労働が,疲労の蓄積をもたらす重要な要因と考えられ,さらには,脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている中で,今般,長時間労働に伴う健康障害の増加など,労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており,これに対処するため2006年に労働安全衛生法が改正されました。
【時間外・休日労働時間の削減】
(1) 36協定は,限度基準に適合するよう定めます。
・限度時間を超えて一定の時間まで労働時間を延長することができる「特別の事情」は,臨時的なものに限るとされていることに留意するものとします。
・月45時間を超えて時間外労働をさせることが可能な場合でも,実際の時間外労働を月45時間以下とするように努めるものとします。
・休日労働を削減するよう努めるものとします。
(2) 年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり,計画的付与制度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図るものとします。
【労働者の健康管理対策】
定期健康診断を実施し,特に深夜業を含む業務に常時従事する労働者には,6箇月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施する必要があります。また,その結果,有所見者については,健康保持のために必要な措置について医師の所見を聴き,適切な事後措置を実施する必要があります。
時間外・休日時間労働が1月当たり100時間を超える労働者であって,本人の申し出があった者については,医師による面接指導が義務付けられました。
時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者及び2~6箇月平均で1月当たり80時間を超える労働者であって本人の申し出があった者については,医師による面接指導を実施するよう努める必要があります。
時間外・休日労働時間がひと月当たり45時間を超える労働者であって健康への配慮が必要と認めた者については,医師の面接指導の措置を講じることが望ましいとされました。
女性労働者の健康管理
母性保護のため,生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が2012年4月10日公布され,10月1日から施行されています。
改正女性則では,妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質を規制対象とし,これらを扱う作業場のうち,以下の業務については,妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業が禁止されています。
・労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い,「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
・タンク内,船倉内での業務など,規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく,呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
職場におけるメンタルヘルス対策
長時間労働,職場における複雑な人間関係等を背景として,労働者の受けるストレスは拡大傾向にあり,また,精神障害等の労災補償も,請求件数,認定件数ともに増加傾向にあります。こうした状況を踏まえて,厚生労働省は,職場における労働者の心の健康を保持するため,事業者が行うことが望ましい措置の具体的な方法を示しています。
【メンタルヘルスケアの基本的な考え方】
事業者は,メンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し,衛生委員会等において十分調査審議を行い,「心の健康づくり計画」を策定する必要があります。 その実施に当たっては,「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われるよう,教育研修・情報提供を行い,4つのケアを効果的に推進し,職場環境等の改善,メンタルヘルス不調への対応,職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。
【メンタルヘルスケア推進の留意事項】
・心の健康問題の特性
・労働の個人情報の保護への配慮
・人事労務管理との連携 ・家庭・個人生活等職場以外の問題
【心の健康づくりの4つのケア】
(1) セルフケア(労働者自身による対処):労働者に対するセルフケアに関する教育研修・情報提供 相談体制の整備,相談しやすい環境の整備
(2) ラインによるケア(管理監督者による対処):管理監督者に対する教育研修・情報提供,職場環境等の把握と改善,労働者からの相談に対応できる体制の整備
(3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医,衛生管理者,保健師等による対処)
(4) 事業場外資源によるケア(外部機関等による支援)