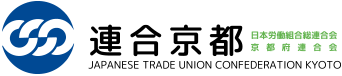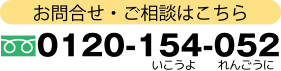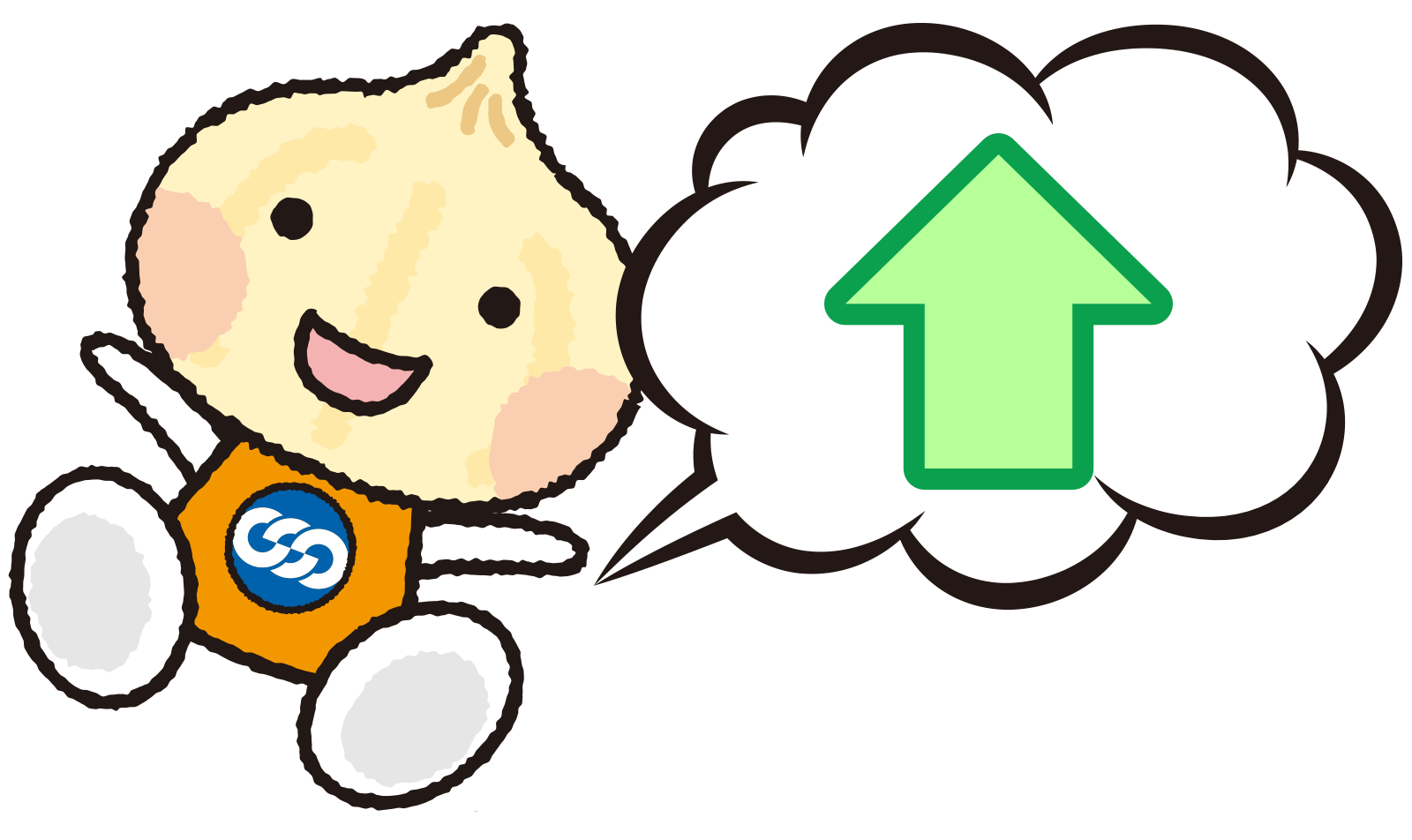【労働時間法制ニュース 第4号】新たな指針に盛り込むべき事項はなにか、休日労働の在り方等について意見が相次ぐ。
【労働時間法制ニュース 第4号】
新たな指針に盛り込むべき事項はなにか、
休日労働の在り方等について意見が相次ぐ。
4月27日、第133回労働政策審議会労働条件分科会(以下、分科会)が開催された。
労働政策審議会任期開始後、初の分科会の開催となるため、新たに任命された委員の紹介が行われた後、時間外労働の上限規制等について、事務局より提示された「論点について(事務局案)」の各論点について、議論を重ねた。
今回は主に、論点の「①時間外労働の上限規制」のうち、(1)限度時間等、(2)適用除外等の取扱い、(3)新たな指針に盛り込むべき事項について、議論した。
(※)配付資料「論点について(事務局案)」、「論点に関する参考資料」については、添付資料をご参照。
記
Ⅰ.日 時:2017年4月27日(木)18:00~19:20
Ⅱ.場 所:中央労働委員会講堂(労働委員会会館7階)
Ⅲ.参加者:公益委員(荒木分科会長、安藤、川田、水島、守島)
労働者側委員(川野、神田、柴田、冨田、八野、福田、村上、世永)
使用者側委員(秋田(代理:滝澤)、小林、斎藤、早乙女、杉山、三輪、輪島) ※敬称略
Ⅳ.議 題:・時間外労働の上限規制等について
・その他
Ⅴ. 概 要:労働政策審議会任期開始後の分科会開催のため、新たに任命された委員の紹介が行われた後、時間外労働の上限規制等について、事務局より「論点について(事務局案)」が提示され、議論を重ねた。主な議論は以下のとおり。
(分)=分科会長、(公)=公益側、(労)=労働者側、(使)=使用者側、(事)=事務局
Ⅵ. 内 容:
1.「(1)限度時間等」について
(労) ①時間外労働の上限規制は、現行の限度基準告示のとおり、労基法に規定する法定労働時間を超える時間に対して適用とされるという考え方で特段の異論はない。労基法は最低限の労働条件を定めた法律であること、36条は32条で定める労働時間の大原則があっての免罰効であることを踏まえれば、「これ以上は絶対に上回ることはできない」ことが明確に分かる条文であるべき。②36協定で延長時間を定める対象期間は、現行告示の3か月等の対象期間を定めると単月の上限は定めないため、各月の配分によっては特別条項なく45時間超えを許容することなる。よって、事務局案の「1日」、「1か月」、「1年」の3区分に整理することに賛成。現在、3か月単位で36協定を締結している事業場もあり、区分変更の十分な周知が必要。
(労) ①特例要件に違反することがないよう、1年単位の規制の区切りはあらかじめ決めて、起算点から1年の間の規制とするとともに、3か月の単位の協定や、協定を出し直した場合にも、1年単位で通算して規制をかけるべき。②労災認定基準との整合性から、2ないし6か月平均80時間以内の計算方法は、協定の対象期間内はもちろん、協定の対象期間をまたがる場合もリセットせずに含めたものとすべき。
(事) 起算日の脱法防止に向け、運用の仕組みを検討する。
(労) 変形労働時間制の制度趣旨を踏まえ、1年単位の変形労働時間制は、事務局案にて特段の異論はない。
(労) 休日労働を含んで複数月平均80時間以内、単月100時間未満の限度は、特例を活用しない通常の月にも適用するという考えに異論はない。安易に休日労働を悪用しないことや休日労働は法定休日の労働であることを周知することが重要。
(使) 年間の法定休日労働の実績の、休日労働をしない者を含んだ平均日数は。
(事) 実績ありの者の平均は全体で5.4日。休日労働の実績がない78.9%の者を合算した際の平均は1.1日となる。
2.「(2)適用除外等の取扱い」について
(労) トラック事業者の労働基準関係法令違反について、監督実施結果は2012年以降悪化しており、その違反の多くが労働時間に関する内容。これは、人手不足が大きな要因であり、労働環境を改善しない限り、悪化に歯止めはかからない。分科会の総意として、原則的上限(月45時間・年360時間)に近づける努力が重要との考え方は理解。長時間労働是正や過労死・自殺者ゼロに向け、関係労使と所管官庁も交えた検討の場を設けるなど、早期に具体的な施策を講じて頂きたい。
(労) 建設事業について、5年後に一般則を適用することについては、前向きに受け止める。人材の確保は、技能・技術向上だけでなく、社会基盤の強化を通じた我が国の発展にもつながるもの。実行計画を踏まえ、着実に歩を進めることが重要。
(事) 自動車運転の業務および建設業務について、検討の場の早期立ち上げ等、段階的な労働時間短縮を進めていく。
(労) ①医師に関しては、医療界だけでなく、現場で働く者の声を踏まえた検討を進めるべき。②適用除外(局長指定事業・業務)については、現行告示同様、年360時間の限度時間の適用を維持すべき。
(使) 午前中に開催した過労死等防止対策推進協議会でも、当事者委員からも発言があったので紹介してほしい。
(事) 本日午前の協議会でも、過労死ゼロの出発点は過労死等防止対策推進法であることを踏まえてほしい旨や、実行計画に対する評価と懸念等の意見があった。
3.「(3)新たな指針に盛り込むべき事項」について
(労) 指針に盛り込むべき内容について、事務局案の4点に異論はない。その上で、「特例の場合に実施する健康・福祉確保措置の内容の例示」は、2015年の建議を踏まえ、現行の裁量労働制指針を参考に例示列挙し、個別企業労使が措置内容の1つ以上を決定し、確実に措置を講じるようにすべき。
(労) 次回分科会に向けて要望。新技術・新商品等の研究開発については、業務の内容が抽象的なため、具体的にどのような要素が該当するのか、どのくらいの者がこの業務に該当し適用除外となっているのか、実態が分かる資料を出してほしい。
(労) 時間外・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、新たな指針に、「休日労働についてもできる限り抑制するよう努めなければならない」ことを盛り込むことが必要。あわせて、法定休日の特定や法定休日労働の回数等に関する規定について、今後の課題として検討することが必要。
(労) 行政官庁による助言・指導に関し、企業の中には保険的な時間を見込んで36協定を締結したり、中にはそのような協定を締結するように労働基準監督署で指導することがあると聞く。また、中小企業では36協定未締結の事業場が約4割との調査結果が出ているが、これらの事業場で時間外労働をまったく行っていないとは考えられない。実行計画を受け、新たな指針に「特例による延長時間をできる限り短くする努力義務」が規定されるが、上限規制の実効性を担保するはずの指針が形骸化しないよう、労働基準監督署による監督指導等の徹底・強化をお願いしたい。
(労) 「時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結の有無」の厚生労働省調査で、36協定を締結していない理由として、「36協定の存在を知らなかった」、「36協定の締結・届出を失念した」ことが挙げられており、法改正の実効性を高めるためにも36協定の適正化は重要な課題。次回、関連資料を出してほしい。
(労) 健康・福祉確保措置に関し、労働安全衛生法においては、中小・零細企業に適用されない事項もあり、新たな指針にどのように盛り込んでいくかもポイント。
(分) 次回以降、引き続き各論点について議論を深めていただきたい。
以 上
(添付資料)
リンクファイルに関するご案内
ご利用のブラウザによっては、ページ内にリンクされているファイル(主にPDFファイル)が
うまく表示されない場合がございます。
その際は、お使いの端末内の設定を変更していただく事で解消されるケースが多く、
お手数ですが、検索エンジンで「○○○(お使いのブラウザの名前) PDF 表示されない」などと検索していただき、
解決方法に従い調整をお願いいたします