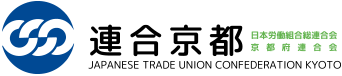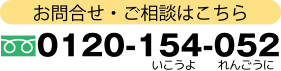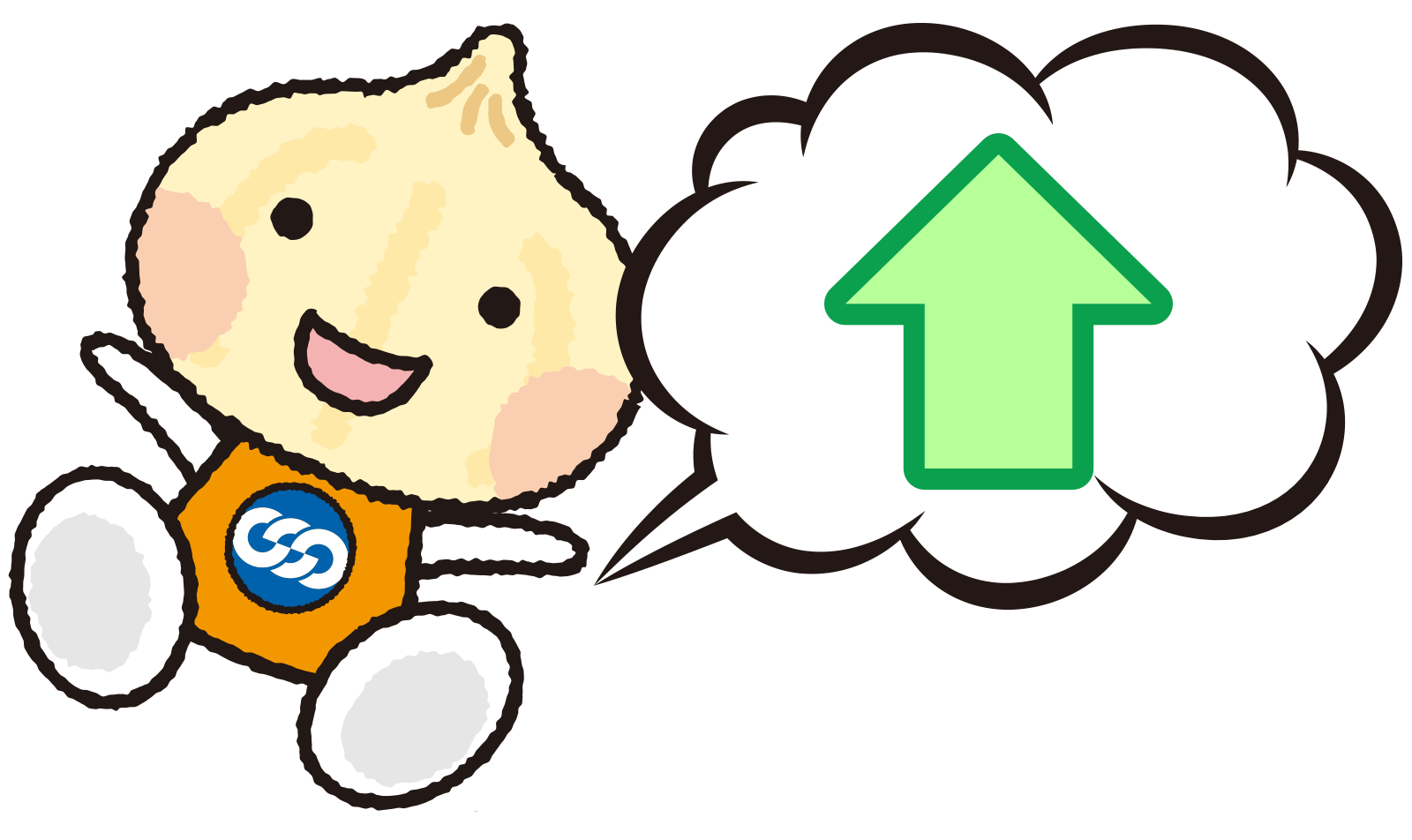【2018「働き方改革」関連ニュース 48号】労働政策審議会労働条件分科会において、時間外労働の上限規制等、「働き方改革関連法」に関する省令・指針事項の検討がスタート!
「働き方改革関連法」に関する省令・指針事項の検討がスタート!
分科会では、冒頭に山越基準局長より、裁量労働制のデータ問題についての謝罪を含めた挨拶がなされた後、事務局より、「経済財政運営と改革の基本方針2018」等について報告がなされた。その後、働き方改革関連として、平成25年度労働時間等総合実態調査結果の精査や「働き方改革関連法案」の与党及び国会における審議の状況、「今後議論いただく省令や指針に定める項目(案)」について説明がなされ、議論を行った。
なお、省令・指針の議論に関しては、事務局案に基づき、第一段階として、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の義務付けなどに関する省令や指針に関する事項の検討・策定を行い、第二段階として、高度プロフェッショナル制度に関する事項の検討を行うことが確認された。
(※)配付資料「『経済財政運営と改革の基本方針2018』等について」等は、添付資料をご参照。
Ⅱ.場 所:中央労働委員会講堂
Ⅲ.参加者:公益委員(荒木分科会長、安藤、川田、黒田、水島、守島)
労働者側委員(川野、柴田、中川、八野、村上、弥久末、世永)
使用者側委員(秋田、斎藤、早乙女、佐久間、杉山、松永、輪島)※敬称略
Ⅳ.議 題:1.報告事項
2.「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
3.その他
Ⅴ. 概 要:事務局より、「経済財政運営と改革の基本方針2018」等について報告がなされたのち、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関して、平成25年度労働時間等総合実態調査結果の精査や「働き方改革関連法案」の与党及び国会における審議の状況、さらに「今後議論いただく省令や指針に定める項目(案)」について説明がなされた。主な議論の内容は以下のとおり。
(分)=分科会長、(公)=公益側、(労)=労働者側、(使)=使用者側、(事)=事務局Ⅵ. 内 容:
1.報告事項:「経済財政運営と改革の基本方針2018」等
(労) 「未来投資戦略2018」に関して、①副業・兼業の場合、長時間労働にならないことや使用者による労働時間・健康管理が必要不可欠となる。加えて、複数就業時における社会・労働保険適用や給付等の課題もあるなか、今後どのように検討を進め、結論を得るのか。②解雇無効時の金銭救済制度の検討についての記載があるが、法技術的・政策的課題が山積される中で制度導入ありきの検討は行うべきではない。
(事) 複数就業時の労災保険などは、検討会・部会での議論が行われるが、公労使で話し合いを積み重ねていく必要があり、出口は未定。
(使) 「規制改革実施計画」の行政手続コスト削減に関して、36協定や就業規則の電子申請の普及につき、取り組みをお願いしたい。
(労) 「未来投資戦略2018」の国家戦略特区の推進の項目で、外国人労働者への賃金支払いを円滑化する新たな賃金支払い方法の導入可能性が盛り込まれているが、仮に外国人労働者が口座を開設できないケースがあるとすれば、労働基準法第24条で規定しているとおり、通貨払いをすれば足りるのではないか。
(事) 国家戦略特区諮問会議で「賃金の確実な支払い等の労働者保護に留意しながら検討していきたい」と厚生労働副大臣が述べており、今後具体的検討を進めたい。
(労) 労基法第24条の意義(通貨払・全額払)を踏まえれば、慎重な検討が必要だ。
2.平成25年度労働時間等総合実態調査結果の精査について
(使) 調査データのミスにより、法案から裁量労働制の対象業務拡大が削除された。柔軟な働き方の選択肢の一つであり、誠に遺憾。二度とないようにしていただきたい。裁量労働制の対象業務拡大については、今後再調査の上、労政審で議論となるが、厚労省においては、法案の早期再提出に向け、環境が整うようにお願いしたい。
(労) データの問題に関わらず裁量労働制の対象業務拡大は必要ないと考えている。公的データは重要なものであり、調査時や調査結果集約時にも慎重さが求められる。時間や人員等の制約がある中での調査を行うこともあると思うが、調査目的を明らかにした上で調査手法を構築し、実施後には内容精査を確実に行っていただきたい。また、調査的監督は労働基準監督官が実態調査と労基署の臨検監督を同時に実施するもの。監督官の業務は多岐に亘り、今後働き方改革法の施行にあたり役割は増していく。こうした観点も踏まえた検討をお願いしたい。
(公) 労働時間実態把握のために適切なデータは何かということを考えた時、睡眠時間や生活時間等、切り口は様々ある。事業場に調査することも重要だが、労働者に問うデータも必要。制度適用による労働時間変化は別制度の者を比較しても意味がなく、同一個人の制度変更前後を追跡調査しないと労働者への影響把握は困難では。
(公) データ不備の問題に関して、分科会の役割の重要性に鑑みると、前提となるデータの重要性が十分に担保されていることが必要であることを強く申し上げる。
3.「働き方改革関連法案」に係る与党及び国会における審議の状況について
(労) ①中小企業の施行期日が先送りになったが、施行までの間にも、中小企業が労働環境の整備や改正法に対応した準備に着実に取り組むことができるよう、必要な対策を強力に進めていただきたい。②中小企業では著しく短い納期の設定等の取引慣行の問題が大きく、自社だけで解決が困難な場合がある。取引関係で弱い立場にある中小企業にしわ寄せが行かないよう、新設される協議会の場で実効性ある議論を行うともに、法改正の内容の周知にも努めていただきたい。③改正された法律を定着させるには職場の労使の取り組みが何より重要。労働組合との集団的労使関係や労使自治の重要性やその機能についても、理解を広げられるようにしてほしい。
(使) 何に取り組んで良いか分からない中小企業に対するアプローチを強化するとともに、中小企業に対する過度なしわ寄せがないよう、監督強化をお願いしたい。
4.今後議論いただく省令や指針に定める事項について
(労) ①今後の法施行に当たっての進め方につき、事務局案では、「省令や指針を策定するタイミングを2段階に分けてはどうか」とあるが、具体的には、第一段階として、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の義務付けなどに関する省令や指針に関する事項の検討・策定を行い、第二段階として、高度プロフェッショナル制度に関する事項の検討を行うという認識で間違いないか。②今後の議論に際し、実際に36協定の様式案も提示いただきながら、具体的に議論を進めていきたい。
(事) ①ご指摘のとおり。②今後、36協定の新様式等をお示ししたい。
(労) 建設事業の対象とする範囲に関して、限度基準告示の内容に加え、省令案では「工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)」が挙げられている。業務の一体性や安全確保の観点から一定程度理解はするが、交通誘導警備を担う者の高齢化等、健康上や安全の配慮が必要。副次的な災害が起きないよう、環境整備が必要不可欠だ。
(労) 自動車運転業務における兼業ドライバーに対する適用範囲の明確化やスピード感を持った改善基準告示の見直しに関して、次回以降も意見を述べていきたい。
(使) 二段階の検討に賛成。システム対応もあり、一刻も早く省令等を示してほしい。
(労) 早期の周知の必要性から、二段階の検討は了解している。ただし、高プロについて「早期に結論を得る」とあるが、きちんと内容を議論する必要がある。
(添付資料)
- 議事次第
- 資料No.1 「経済財政運営と改革の基本方針2018」等について
- 資料No.2 成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直し(社会保険労務士法の改正)について(報告)
- 資料No.2-2 社会保険労務士法新旧対照表
- 資料No.2-3 参照条文
- 資料No.3-1 平成25年度労働時間等総合実態調査結果の精査について
- 資料No.4-1 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に係る与党及び国会における審議の状況について
- 資料No.4-2 衆議院における附帯決議
- 資料No.4-3 参議院における附帯決議
- 資料No.5 今後議論いただく省令や指針に定める項目について(案)
リンクファイルに関するご案内
ご利用のブラウザによっては、ページ内にリンクされているファイル(主にPDFファイル)が
うまく表示されない場合がございます。
その際は、お使いの端末内の設定を変更していただく事で解消されるケースが多く、
お手数ですが、検索エンジンで「○○○(お使いのブラウザの名前) PDF 表示されない」などと検索していただき、
解決方法に従い調整をお願いいたします